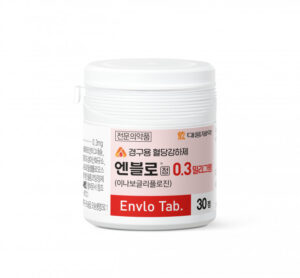建国大学グローバル植物ストレス研究センターのユン・ダジン教授の研究チームが、植物が干ばつに耐える過程で核心的な役割を果たす転写調節因子の活性化メカニズムを新たに明らかにした。今回の研究結果は、植物科学及び農業分野で権威ある国際学術誌New Phytologist(IF=8.3)に1月31日にオンライン掲載された。
ユン・ダジン教授(筆頭著者、建国大学医生命工学科)、シャザリン博士(第1著者、建国大学グローバル植物ストレス研究センター)、アリ・アクタ博士(共同第1著者、建国大学グローバル植物ストレス研究センター)などが参加した今回の研究では、植物が乾燥した環境で干ばつ抵抗性遺伝子の発現を調節するタンパク質の生成と消滅過程を分子レベルで分析した。
植物は移動できないが、環境変化に適応する能力を備えている。乾燥した環境にさらされると、植物はABA(アブシジン酸)というストレスホルモンを生成し、このホルモンが信号を伝達して気孔を閉じて水分の蒸発を防ぐ方法で生存を助ける。このような過程で重要な役割を果たすのが、生体防御遺伝子の発現を調節する転写調節因子だ。
これまで、転写調節因子がいつ、どのように生成され、分解されるかについての分子的メカニズムは明らかにされていなかった。 しかし、研究チームは今回の研究を通じて、植物が外部環境の変化に対応する過程で転写調節因子の生成を調節するメカニズムを解明し、これを基に干ばつ抵抗性植物の開発の基盤を築いた。
現在、世界の陸地の40%以上が砂漠化しており、これは食糧生産の減少と環境問題につながり、人類の生存にも影響を及ぼす重要な問題だ。これに伴い、多くの研究者が乾燥した環境でも生存できる作物を開発するために努力している。今回の研究は単純な学術的成果を超えて、気候変動による農業問題の解決に実質的な貢献をすることが期待される。研究チームは、今回の研究結果が干ばつに強い作物開発の礎となり、気候変動時代の食糧問題解決に役立つことを期待していると明らかにした。
一方、建国大学グローバル植物ストレス研究センターは、2024年科学技術情報通信部の先導研究センター事業に選定され、7年間合計112億ウォンの研究費を支援される。研究センターは、気候変動に対応するための植物の環境ストレスシグナル伝達及び生体防御機構を集中的に研究し、これを通じ、未来の食糧及び環境問題の解決に先導する計画だ。